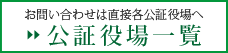公証事務
1公正証書
Q1. 公正証書とは、どのようなものですか?
公正証書とは、私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことです。
公文書は、文書の成立について真正であるとの強い推定(形式的証明力)が働きます。公証人が当事者の嘱託により作成した文書には、公正の効力が生じ、反証のない限り、完全な証拠力を有しております。このように公正証書は、極めて強力な証拠力を有しております。
また、金銭消費貸借契約等の金銭の支払を目的とする債務についての公正証書に、①一定額の金銭の支払についての合意と、②債務者が金銭の支払をしないときは、直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている場合には、金銭債務の不履行があったときは、裁判手続を経ることなく、直ちに強制執行をすることができます。この強制執行力をすることができる公正証書のことを「執行証書」といいます。
上記のように、公正証書は、皆様の大切な権利の保全とその迅速な実現のために、非常に大きな役割を果たしております。
Q2. 公正証書には、どのようなものがありますか?
公正証書には、法律行為に関する公正証書(契約や遺言等)と、私権に関する事実についての公正証書(知的財産権の管理や貸金庫の開扉、尊厳死宣言等)がありますが、具体的には、次のようなものです。
(1) 法律行為に関するもの
- 当事者間の契約に関する公正証書
土地や建物の売買、賃貸借、金銭消費貸借等の契約に関する公正証書が一般的ですが、それ以外にも、機械器具のリース契約等、法令や公序良俗に反するなどの無効原因がなく、行為能力の制限による取消しの対象とならない限り、どのような内容の契約でも、公正証書を作成することができます。 - 嘱託人による単独行為に関する公正証書
当事者間の合意を契約として公正証書にするだけでなく、嘱託人一人の意思表示の内容を文書で明らかにする単独行為に関する公正証書の作成も行われています。
遺言は、その典型であり、遺言者による単独の法律行為です。具体的には、遺言者が自分の死後に、その財産を誰にどのような割合で残すのかを決めたり、自分を虐待するなどした相続人を廃除したり、婚外子を認知したり、先祖のお墓を誰に守ってもらうかを定めたりします。遺言公正証書は、遺言者の話した遺言の内容を公証人が聞き取り、その内容を公正証書にまとめて作成します。聴覚や言語機能に障害のある方でも、公正証書遺言をすることができます。
そのほか、単独行為に関する公正証書には、保証意思宣明公正証書等があります。
(2) 私権に関する事実についての公正証書(事実実験公正証書)
公証人が、自ら実験、すなわち五官の作用で認識した結果を記述する公正証書を事実実験公正証書といいます。事実実験の結果を記載した「事実実験公正証書」は、証拠を保全する機能を有し、権利に関係のある多種多様な事実を対象とします。
例えば、特許権者の嘱託により、特許権の侵害されている状況を記録した事実実験公正証書を作成する場合や、相続人から嘱託を受け、相続財産把握のため被相続人名義の銀行の貸金庫を開披し、その内容物を点検・確認する事実実験公正証書を作成する場合があります。
事実実験公正証書は、その原本が公証役場に保存される上、公務員である公証人によって作成された公文書として、高度の証明力を有します。
そのほか、人の意思表示や供述の内容もこの証書で証拠化することができます。例えば、いわゆる尊厳死の意思表示をこの事実実験公正証書に記載しておくことが可能です。将来の紛争を防止するという目的のために、非常に活用範囲の広い公正証書です。
Q3. 公正証書は、本人でなければ作成できないのでしょうか?
次の①~③の場合を除き、本人の委任状を持った代理人によって、公正証書の作成ができます。ただし、売買契約等の代理が許される公正証書でも、原則として双方の代理を一人で行うことはできません。
(本人しかできない公正証書)
- 遺言は、公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取り、これを公正証書に記載し、これを遺言者と証人2名以上の前で読み上げて、その内容に間違いがないことを確認して作成するもので、代理人によってすることはできません
なお、代理が許されないといっても、第三者が関与してはならないという趣旨ではありません。遺言公正証書作成の際、本人が公証人の面前で遺言の内容を話し、公正証書に署名押印する必要があるというだけです。遺言公正証書作成の準備段階において遺言者本人の家族や士業者らの関係者が本人の使者として遺言作成に必要な資料を公証役場に持参し、本人の意思を公証人に伝えることは何ら問題がありません。 - 任意後見や遺言信託等、公証人が委任者本人の判断能力及び契約意思を確認する必要がある契約については、委任者の代理は、原則として認められません。しかし、委任者が入所している老人ホームにおいてコロナの感染状況により面会を禁止しているなどの事情がある場合に限って例外的に代理による作成も認めていますので、公証役場にご相談ください。なお、その場合でも、公証人がテレビ電話によって委任者本人の意思確認をすることにしております。
- 保証意思宣明公正証書については、保証人になる人(保証予定者)が保証の意味やリスクを十分に理解しないまま、安易に保証契約を締結することを防ぐことを目的としています。公証人が保証予定者の保証意思を確認した上で、公正証書を作成しますので、代理人によってすることはできません。
Q4. 公正証書のデジタル化とはどういうものですか?
- 令和7年10月1日に公証人法が改正され、同日以後に法務大臣が指定する公証人が作成する公正証書については、原則として電磁的記録で作成されることとなりました。
従来、公正証書は、紙で作成され、嘱託人等の列席者と公証人がそれぞれ署名押印をしたものが原本でしたが、今後は、PDF形式の電磁的記録で作成され、嘱託人等の列席者がパソコンを使用して電子サインを付し、公証人が同じく電子サインと官職証明書による電子署名を付したものが原本となります。 - 公正証書のデジタル化により、嘱託人の申出があり、他の嘱託人に異議がなく、公証人が相当と認めた場合には、列席者が公証役場に行かなくても、ウェブ会議により公証人や他の列席者と相互の状況を確認しながら通話する方法(以下「リモート方式」といいます。)で公正証書を作成できるようになります。
- 紙で作成された公正証書原本は、公証役場で保管されますが、電磁的記録で作成された公正証書原本は、日本公証人連合会が運営するシステムのそれぞれの公証人が管理する領域で保存されます。この保存領域には、公正証書を作成した公証人及び後任公証人等その公証人の事務を取り扱うこととされた公証人並びにこれらの公証人の書記のみがアクセスできることとされています。
(「公証事務」のページ内の各Qに対する答の中の「公証役場に保管」には、日本公証人連合会の運営するシステムのその公証人が管理する領域での保管を含みます。) - 公正証書の内容を証明するものとして、従来は正本、謄本が紙の文書として発行されていましたが、電磁的記録で作成された公正証書については、これらを従前どおり公証人の署名押印がされた紙の文書として発行することも、公証人の官職証明書による電子署名が付された電磁的記録として発行することも可能となります。これらが電磁的記録として発行された場合、Adobe社のPDFファイル閲覧ソフトで読み込むと、電子署名の真正性、有効性や電子署名後に改ざんのないことが確認できます。
Q5. 公正証書の原本を紙で作成するか、電磁的記録で作成するかを選択することはできますか?
- 公証人法で、電磁的記録をもって公正証書を作成することが困難な事情がある場合以外は、電磁的記録で公正証書を作成することとされていますので、嘱託人が公正証書を紙で作成するか、電磁的記録で作成するかを選択することはできません。
- 電磁的記録で公正証書を作成することが困難な事情としては、
①法律上、書面で作成することが前提となっている場合(列席者の署名押印が義務づけられている保証意思宣明公正証書及び成年被後見人の遺言公正証書、券面又は付箋への記載が必要な手形・小切手の拒絶証書など)、
②技術的・物理的に困難な場合(PDF化することが困難な大きな図面を添付する必要があるとき、機材の故障により電磁的記録としての作成ができないときなど)
などがこれに当たると考えられます。
Q6. 公正証書のデジタル化により、公証人と対面で行う公正証書の作成は、どのように変わりますか?
これまで紙で作成していた公正証書の原本を、パソコン上で電磁的記録として作成することになるため、紙の公正証書に行っていた署名押印に変わって、パソコン上でタッチペンを使って電子サインを行うことになる点が相違点ですが、筆記用具が変わる程度の変化で、大きくは変わりません。
Q7. リモート方式の利用ができるのは、どのような場合ですか?
- リモート方式の利用ができるのは、
①嘱託人の申出があること、
②通訳人、証人のみのウェブ会議での参加を除き、他の嘱託人の異議がないこと、
③公証人が相当と認めること
の全ての要件が満たされた場合です。
なお、保証意思宣明公正証書については、公証人法上、ウェブ会議による作成はできないこととされています。 - ウェブ会議方式での公正証書の作成が相当かどうかについては、その必要性と許容性とを総合的に勘案して判断することとされています。
ウェブ会議方式での参加を希望する人が、心身の状況、就業状況、地理的状況等に照らして公証役場に行くことが困難な場合や、嘱託人相互の関係から嘱託人相互が同席することに問題がある場合、感染症予防等のため嘱託人がいる施設への立入が制限されている場合などは、必要性が高いと考えられます。
一方、許容性は、嘱託人の本人確認、真意の確認、判断能力の確認等を適切に行うことができるかどうかという観点から判断され、代理人による手続が許容されるような場合には許容性は高いと考えられますが、遺言、任意後見等、本人の意思の確認が重要なものについては、慎重に判断されることになります。
また、ウェブ会議中に、電子サイン等のための機材操作をしていただく必要がありますので、そのような操作が困難な場合は、許容性に欠けると判断されます。 - リモート方式の利用の上での留意点などにつきましては、「リモート方式に関する説明」をごらんください。
Q8. リモート方式の利用に必要な機材を教えてください。
- まず、ウェブ会議に参加するための機材等として、①パソコン、②カメラ、マイク、スピーカーが必要です。
タブレット型PCやスマートフォンは、電子サインを行う際に、公証人や他の列席者が、画面上の電子サインの状況と電子サインを行っている列席者の様子を同時に確認することができないため、リモート方式による公正証書の作成には使用できません。また、パソコンのOSやウェブブラウザのバージョンが古いものである場合には、使用できない場合があるのでご注意ください。
(注)令和7年10月時点で利用可能なOS等
・OS:Windows10、Windows11、または最新3つのバージョンのMacOS
・Windowsにインストールされている.NETのバージョン:NET 4.5CLR以降
・ブラウザ:最新3つのバージョンのMicrosoft Edge、Google Chrome、Fire fox、又は最新2つのバージョンのSafari - リモート方式での公正証書作成の場合も、列席者は、公正証書が正確に記録されていることを確認した後、クラウド上の公正証書のPDF原本に電子サインをする必要があります。そのため、③電子サインの際に使用するタッチ入力が可能なディスプレイ又はペンタブレット及びタッチペンが必要です。
- また、ウェブ会議には、公証人が送付した招待メールから参加していただくことになりますし、電子サインも、公証人から送付された電子サイン依頼メールで手続を開始していただくことになるため、④ウェブ会議中に使用するパソコンで送受信可能なメールアドレスを用意していただく必要があります。
Q9. リモート方式の申込みは、どうすればよいですか?
- リモート方式の利用の希望がある場合、リモート方式の要件が整っているか、リモート方式での公正証書の作成が相当かについての公証人の判断が必要となりますので、早めに公証人に相談していただく必要があります。なお、事前の相談の段階でリモート方式を利用できるものと判断された場合でも、実際に手続を開始した後の状況で、リモート方式の利用が相当でないと判断され、リモート方式による公正証書の作成手続が取り止めとなる場合もあり得ますので、ご承知おきください。
- リモート方式の利用に際しては、事前に、ウェブ会議での参加を希望する人の氏名、その人についてウェブ会議の利用を希望する理由、その人がウェブ会議の招待及びウェブ会議中のメールの送受信に使用するメールアドレス等を記載したウェブ会議利用申出書の提出が必要です。申出書の様式は、公正証書作成嘱託書を兼ねた様式1をご利用ください。
- リモート方式を利用する場合、本人確認資料として、印鑑登録証明書又は署名用電子証明書の提出が必要となります。
印鑑登録証明書の提出の場合は、公正証書の最終の案文を添付するなど適宜の方法で嘱託の内容を明らかにした公正証書作成嘱託書を紙で作成して実印を押捺し、これと印鑑登録証明書を郵送等の方法により提出することになります。
署名用電子証明書の提出の場合は、上記と同様の公正証書作成嘱託書をPDFファイルとして作成し、これにマイナンバーカードの署名用電子証明書その他の法務大臣が指定する電子証明書で電子署名したものを電子メール等で提出することになります。
上記の公正証書作成嘱託書は、上記2のウェブ会議利用申出書を兼ねたものとして作成することも可能です(様式1)。
なお、いずれの場合も、リモート方式で参加する嘱託人・嘱託代理人の顔写真が貼付された公的身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)の写しを事前に送付していただき、ウェブ会議の冒頭で、その原本を画面上で提示していただくこととなります。 - リモート方式の利用の上での留意点などにつきましては、「リモート方式に関する説明」をごらんください。