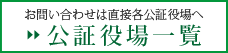公証事務
2遺言
1 遺言の意義および種類
Q1.そもそも、何のために遺言をするのですか?
- 遺言の意義
遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ、守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示です(なお、遺言には、非嫡出子を認知するなどの身分上の事項に関する遺言もありますが、このQ&A では、財産上の事項に関する遺言について説明することにします。)。 - 遺言による相続争いの防止
世の中では、遺言がないために、相続をめぐり、親族間で争いの起こることが少なくありません。しかし、今まで仲の良かった者が、相続をめぐって骨肉の争いを起こすことほど、悲しいことはありません。
遺言は、上記のような悲劇を防止するため、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続をめぐる争いを防止しようとする目的があります。また、大切な遺族に対して「最期のメッセージを遺す」という意味もあります。
Q2.遺言がないときは、どうなりますか?
- 法定相続
遺言がないときは、民法が相続人の相続分を定めているので、これに従って遺産を分けることになります(これを「法定相続」といいます。)。 - 遺言がないときは遺産分割協議が必要
ところで、民法は、例えば、「子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする」というように、抽象的に相続分の割合を定めているだけなので(民法900 条)、遺産の帰属を具体的に決めるためには、相続人全員で遺産分割の協議をする必要があります。
しかし、少しでも多く、少しでも良いものを取りたいというのが人情なので、協議をまとめるのは、必ずしも容易なことではありません。協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で調停または審判で解決してもらうことになりますが、この場合でも、争いが深刻化して、解決が困難になる事例が後を絶ちません。
それに対し、遺言で、例えば、妻には自宅と○万円、長男にはマンションと□万円、二男には別の土地と◇万円、長女には貴金属類と△万円といったように具体的に決めておけば、遺言に基づいて相続手続をスムーズに行うことができることから、争いを未然に防ぐことができるわけです。もとより、遺留分侵害額請求があれば、紛争は残りますが、遺言がある場合には、相続人が被相続人の意思を尊重して遺留分の主張を思いとどまる場合もあるとされています。 - 遺言による公平な遺産相続の実現
また、法定相続に関する規定は、一般的な家族関係を想定して設けられているので、これをそれぞれの具体的な家族関係に当てはめると、相続人間の実質的な公平が図れないという場合も少なくありません。
例えば、法定相続では、子は、皆等しく平等の相続分を有していますが、子供の頃から遺言者と一緒になって家業を助け、苦労や困難を共にして頑張ってきた子(家産の維持・増加に努めた子)と、そうではなく余り家に寄り付かない子とでは、それなりの差を設けないと、かえって不公平ということにもなります。法定相続でも、寄与分の制度はありますが、寄与分が認められるための手続が煩雑である上、裁判所が認める寄与分は一般の人が思うようなものではないとされています。
すなわち、遺言者が、自分の家族関係をよく頭に入れて、その家族状況に合った相続の仕方を遺言できちんと決めておくことは、後に残された者、とくに家業を助け親の面倒を見てきた者にとって、とても有り難いことであり、必要なことなのです。
Q3.遺言の必要性が特に高い場合とは、どのような場合ですか?
一般的に言えば、ほとんどの場合において、遺言者が、ご自分の家族関係や状況をよく頭に入れて、それにふさわしい形で財産を承継させるように遺言をしておくことが、遺産争いを予防するため、また、後に残された者が困らないために、必要なことであると思います。
とりわけ、次の①から⑦までのような場合には、遺言をしておく必要性が高いといえるでしょう。
- 夫婦の間に子供がいない場合
子供のいない夫婦のうちご主人が死亡した場合で、その両親がすでに亡くなっているときは、法定相続によると、亡夫の財産を、妻が4分の3、亡夫のきょうだいが4分の1の割合で分けることになります。
しかし、長年連れ添った妻に全財産を相続させたいと思う方も多いでしょう。そうするためには、遺言をしておくことが必要なのです。きょうだいには、遺留分がないので、遺言さえしておけば、全財産を大切な妻に残すことができます。 - 再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合
先妻の子と後妻との間では、血縁関係がなく、とかく感情的になりやすいので、遺産争いが起こる確率が高くなるといえます。争いの発生を防ぐため、遺言で相続分をきちんと定めておく必要性が特に高いといえるでしょう。 - 長男の嫁に財産を分けてやりたい場合
長男の死亡後、その妻が亡夫の親(例えば、あなた自身)の世話をしてくれているような場合には、亡長男の妻(嫁)にも財産を残してあげたいと思うことが多いと思いますが、嫁は、相続人ではありません。民法の改正によって特別の寄与の制度が認められるようになりましたが、その制度に基づく場合には、お嫁さんが、相続人に対し、寄与に応じた額の金銭の支払を請求し、当事者間に協議が調わないときなどは、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求する手続をしなければなりません(民法1050 条)。そのような遠回しな手続をしなくても、お嫁さんに遺贈する旨の遺言をすることによって、財産を分けることができます。 - 内縁の妻の場合
長年、夫婦として連れ添ってきても、婚姻届を出していない場合には、いわゆる内縁の夫婦となり、内縁の妻には相続権がありません。内縁の妻に財産を残してあげたい場合には、必ず遺言をしておかなければなりません。 - 家業等を継続させたい場合
個人で事業を経営したり、農業を営んでいたりする場合などは、複数の相続人に分割してしまうと、経営の基盤を失い、事業等の継続が困難となります。このような事態を招くことを避け、家業等を特定の者に承継させたい場合には、家業の維持に必要な資産を事業承継者に相続させ、他の相続人との間では代償金で公平を図るなど、きちんとその旨の遺言をしておかなければなりません。 - 家族関係に応じた適切な財産承継をさせたい場合
上記の各場合のほか、① 特定の財産を特定の相続人に承継させたいとき(例えば、不動産を相続人の共有にしますと、将来、処分する際に、共有者の協議を要することになります。)、② 身体に障害のある子に多く相続させたいとき、③ 老後の面倒を見てくれた子に多く相続させたいとき、④ かわいい孫に財産を残したいときなどのように、遺言者のそれぞれの家族関係の状況に応じて、財産承継をさせたい場合には、遺言をしておく必要があります。 - 相続人が全くいない場合
相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。このような場合に、① 特別世話になった人にお礼として財産を譲りたいとき、② お寺や教会、社会福祉関係の団体、自然保護団体、またはご自分が有意義と思われる各種の研究機関等に寄付したいときなどは、その旨の遺言をしておく必要があります。
Q4.遺言には、どのような種類がありますか?
- 遺言の種類
遺言には、① 公正証書遺言、② 自筆証書遺言、③ 秘密証書遺言の3種類があります。その3種類については、「3 公正証書遺言の作成」以下で詳しくご説明します。 - 厳格な方式の定め
遺言は、遺言者の死亡後に、その意思を確実に実現させる必要があるため、3種類の遺言のいずれについても、法律によって厳格な方式が定められています。その方式に従わない遺言は、全て無効となります。「あの人は、生前にこう言っていた」などといっても、また、録音テープやビデオで録音や録画をしておいても、それらは、遺言として、法律上の効力がありません。
2 遺言の時期、撤回及び変更
Q1.遺言は、いつするべきものでしょうか?
- 万一に備えて家族のために
遺言は、死期が近づいてからするものと思っている方がいますが、それは全くの誤解です。人は、いつ何時、何があるかも分かりません。いつ何があっても、残された家族が困らないように配慮し、遺言書を作成することが望ましいといえます。その点では、生命保険に似ています。
つまり、遺言は、自分が元気なうちに、大切な家族のために、自分に万一のことがあっても、残された者が困らないように作成しておくべきことをお勧めします。最近では、かなり若い人でも、海外旅行に行く前などに遺言書を作成しておく例も増えています。遺言は、後に残される家族に対する最大の思いやりなのです。 - 判断能力がある元気なうちに
遺言は、判断能力があるうちは、死期が近くなってもできますが、判断能力がなくなってしまえば、もう遺言はできません。遺言をしないうちに、判断能力がなくなったり、死んでしまったりしては、取り返しがつきません。そのために、家族の悲しみが倍加する場合もあるでしょう。遺言は、元気なうちに、後の備えとして、これをしておくことが望ましいといえるでしょう。遺言は、満15歳以上であれば、いつでもできます。
Q2.遺言の取消し(撤回)や変更は、自由にできますか?
- 撤回や変更も可能
遺言は、人の最終意思を保護しようという制度ですので、取消し(法律上は、遺言の取消しのことを「撤回」といいます。)や変更は、いつでも、また、何回でもできます。遺言書を作成した時点では、それが最善と思って作成した場合でも、その後の家族関係を取り巻く諸状況が変化し、あるいは心境が変わったり、考えが変わったりして、遺言を撤回し、または変更したいこともあると思います。さらに、財産の内容が大きく変わったとき等も、多くの場合、書き直した方がよいといえるでしょう。 - 撤回や変更のための新たな遺言
以上のように、遺言は、遺言書作成後の諸状況の変化に応じて、いつでも、自由に、撤回や変更をすることができます。ただ、遺言の撤回や変更は、必ず新たな遺言の形式(自筆証書であるか、公正証書であるかの種類は問いません。)でする必要があり、その場合、新たに作成する種類の遺言の方式に従って、適式にされなければなりません。
3 公正証書遺言の作成
Q1.公正証書遺言とは、どのようなものですか?
- 公正証書遺言の作成
公正証書遺言は、遺言者本人が、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が、それが遺言者の真意であることを確認した上、これを文章にまとめたものを、遺言者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧させて、内容に間違いがないことを確認してもらって、遺言公正証書として作成します
なお、民法では、「証人二人以上」と定められていますが、公証実務では、証人が3名以上になることはなく、証人2名で公正証書遺言が作成されます。
遺言者が遺言をする際には、どのような内容の遺言にしようかと思い悩むことも少なくないと思います。そのようなときでも、公証人が、親身になって相談を受け、必要な助言をしますので、遺言者にとって、その意向に沿った最善と思われる遺言書を作成することができます。 - 公正証書遺言の費用
費用がどの程度必要かについてご心配かもしれません。費用は、政令で定められており、相談は、全て無料となっています。詳しくは、Q7をご覧ください。
Q2.公正証書遺言には、どのようなメリットがありますか?
公正証書遺言には、次のように、多くのメリットがあります。
- 安全確実な遺言方法
公証人は、多年、裁判官、検察官または弁護士の経験を有する法曹資格者や、多年、法律事務に携わり、法曹資格者に準ずる学識経験を有する者です。いずれも正確な法律知識と豊富な実務経験を有しています。複雑な内容であっても、法律的に見てきちんと整理した内容の遺言書を作成しますし、言うまでもなく、方式の不備で遺言が無効になるおそれもありません。公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて、安全確実な遺言方法であるといえます。 - 遺言者の自書が不要
自筆証書遺言は、財産目録以外は全文を自ら手書きしなければならないので、体力が弱り、あるいは病気等のために、手書きが困難となった場合には、自筆証書遺言をすることはできません。他方、このような場合でも、公証人に依頼すれば、遺言をすることができます。
また、公正証書遺言では、遺言者が病気等のために電子サインができない場合でも、公証人が、遺言公正証書にその旨を記録又は記載することによって、公正証書を作成できることが法務省令で認められています。 - 公証人の出張が可能
遺言公正証書は、役場以外でも作成することが認められています。例えば、遺言者が高齢で体力が弱り、あるいは病気等のために、公証役場に出向くことが困難な場合などには、公証人が、遺言者のご自宅や老人ホーム、介護施設、病院等に出張して、遺言公正証書を作成することが行われています。なお、離島等で公証役場へのアクセスが困難であったり、感染症予防の観点から公証人等の出張が困難であるなどの事情があり、かつ、遺言者が所在する場所の状況や遺言の内容その他の様々な事情から、遺言者が本人であることの確認や、本人にその遺言をする意思があることの確認に支障がないものとして、公証人が相当と認めた場合には、遺言者が公証役場に行かずに、ウェブ会議で公証人と面談する方法で公正証書を作成することも可能です。 - 遺言書の検認手続が不要
公正証書遺言は、家庭裁判所での検認手続を経る必要がないので、相続の開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。 - 遺言書原本の役場保管
遺言公正証書は、原本が必ず公証役場(電磁的記録で作成された原本の場合は、公証人の団体である日本公証人連合会が運営するシステム)に保管されるので、紛失のおそれはなく、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりするおそれも全くありません。 - 遺言書原本のバックアップシステムの存在
日本公証人連合会では、震災等により、遺言公正証書の原本、正本および謄本が全て滅失した場合でも、その復元ができるようにするため、平成26年以降に作成された全国の遺言公正証書の原本については、これらの電磁的記録(遺言証書PDF)を作成して、二重に保存しています。令和7年に、公正証書が電子化された後は、これらの電磁的記録及び新たに作成された公正証書の原本を日本公証人連合会が運営するシステムで保存しますが、このシステムには、災害等に備えるためバックアップシステムが構築されているので、記録保管の点からも安心です。 - 遺言の効力発生後の相続人等による遺言検索が可能
平成元年以降に作成された遺言公正証書については、遺言の効力発生後、相続人等の利害関係人は、全国の公証役場において、被相続人が公正証書遺言をしたかどうか等を問い合わせることができます。
Q3.公正証書遺言をするには、どのような資料を準備すればよいでしょうか?
公正証書遺言の作成には、次のような資料が必要となります。公証人に相談する場合には、これらの資料を準備していただくと、打合せがスムーズに進行します。
なお、事案に応じ、他にも資料が必要となる場合もありますので、詳細は、最寄りの公証役場にお尋ねください。
- 遺言者本人の3か月以内に発行された印鑑登録証明書
ただし、印鑑登録証明書に代えて、運転免許証、旅券、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(同カードは平成27 年12 月に発行を終了していますが、有効期間内であれば利用できます。)等の官公署発行の顔写真付き身分証明書を遺言者の本人確認資料にすることもできます。 - 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本や除籍謄本
- 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票、手紙、ハガキその他住所の記載のあるもの。法人の場合には、その法人の登記事項証明書または代表者事項証明書(登記簿謄本)
- 不動産の相続の場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
- 預貯金等の相続の場合には、その預貯金通帳等またはその通帳のコピー
- なお、Q1で説明したように、公正証書遺言をする場合には、証人2名が必要ですが、遺言者の方で証人を用意される場合には、証人予定者の氏名、住所および生年月日をメモしたものをご用意ください。
Q4.公正証書遺言は、どのような手順で作成するのですか?
公正証書遺言の作成は、通常、次のような手順で行われます。
- 公証人への遺言の相談や遺言書作成の依頼
公正証書遺言は、士業者や銀行等を介して公証人に相談や作成の依頼をすることもできますが、士業者や銀行等を介することなく、直接、遺言者やその親族等が公証役場に電話やメールをしたり、予約を取って公証役場を訪れたりして、公証人に直接、遺言の相談や遺言書作成の依頼をしても一向に差し支えありません。実際にも、そのような場合が少なくありません。 - 相続内容のメモや必要資料の提出
相談や遺言書の作成に当たっては、相続内容のメモ(遺言者がどのような財産を有していて、それを誰にどのような割合で相続させ、または遺贈したいと考えているのかなどを記載したメモ)を、メール送信、ファックス送信、郵送等により、または持参して、公証人にご提出ください。
また、それとともに、Q3で記載した必要書類を公証人にご提出ください。 - 遺言公正証書(案)の作成と修正
公証人は、前記2で提出されたメモおよび必要資料に基づき、遺言公正証書(案)を作成し、メール等により、それを遺言者等に提示します。
遺言者がそれをご覧になり、修正したい箇所を摘示すれば、公証人は、それに従って遺言公正証書(案)を修正し、確定します。 - 遺言公正証書の作成日時の確定
遺言公正証書(案)が確定した場合には、公証人と遺言者等との間で打合せを行った上で、遺言者に公証役場にお越しいただき、あるいは公証人が遺言者のご自宅や病院等に出張するなどして遺言者が公正証書遺言をする日時を確定します(事案によっては、公正証書遺言をする日が、最初に設定されることもあります。)。 - 遺言の当日の手続
遺言当日には、遺言者本人から公証人に対し、証人2名の前で、遺言の内容を改めて口頭で告げていただきます。公証人は、それが判断能力を有する遺言者の真意であることを確認した上で、前記3の確定した遺言公正証書(案)に基づきあらかじめ準備した遺言公正証書の原本を、遺言者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧させて、遺言の内容に間違いがないことを確認してもらいます(内容に誤りがあれば、その場で修正することもあります。)。
遺言の内容に間違いがない場合には、遺言者および証人2名が、遺言公正証書の原本となる電磁的記録に電子サインをすることになります(遺言者が電子サインをすることができない場合については、Q2 の2 参照)。
そして、公証人も、遺言公正証書の原本となる電磁的記録に電子サインし、電子署名することによって、遺言公正証書が完成します。公証人が電子署名をすると、それ以後に遺言公正証書の内容が書き換えられた場合には、その記録が残るため、遺言書の改ざんが防げます。
遺言当日に以上の手続を行うに際しては、遺言者が自らの真意を任意に述べることができるように、利害関係人には、席を外していただく運用が行われています。
Q5.公正証書遺言の証人は、どのように手配するのですか?
- 遺言者側が手配する場合
公正証書遺言をするためには、遺言者の真意を確認し、手続が適式に行われたことを担保するため、証人2名の立会いが義務づけられています。
証人2名はいずれも、遺言者の方で手配することができますが、① 未成年者、②推定相続人、③ 遺贈を受ける者、④ 推定相続人および遺贈を受ける者の配偶者および直系血族等は、証人になることができません。 - 公証役場で紹介する場合
なお、適当な証人が見当たらない場合には、公証役場で紹介することも可能ですので、遠慮なくお申し出ください。
Q6.公正証書遺言の秘密保持について、説明してください。
公正証書遺言は、次のように、確実に秘密を守ることができる遺言です。遺言を検討されている方は、安心して、公証人にご相談ください。
- 公証人等の守秘義務
公証人は、法務大臣から任命された実質的公務員であり、法律上の守秘義務が課されています。公証人を補助する書記も、職務上知り得た秘密を他に漏らさないことを宣誓して採用されているので、秘密が漏れる心配はありません。
また、証人は、遺言者の依頼に基づいてその場に立ち会うことから、遺言者が遺言書を作成したことや遺言の内容について、遺言者から証人に対し、他に漏らさないようにとの明示の意思表示があったときはもちろんのこと、たとえ明示の意思表示がなくても、遺言の趣旨に照らし、当然、他に漏らさないようにとの黙示の意思表示がなされ、かつ、証人はこれを承諾していると解されるので、証人が遺言者に対して秘密保持義務を負うことは明らかといえます。これは、公証役場が紹介した証人についても、同様に秘密保持義務を負うということができます。
以上のとおり、公証人の側や証人から、遺言公正証書を作成したことや遺言の内容が漏れる心配はありません。 - 遺言書原本の厳重な保管
さらに、遺言公正証書の原本は、公証役場に厳重に保管され、遺言者の死亡まで他人の目に触れることは絶対にありません。実際にも、遺言公正証書に関する情報漏れにより問題が起きたということも聞きません。
Q7.公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?
公正証書遺言の作成費用は、公証人手数料令という政令で法定されています。ここに、その概要を説明しますと、次のとおりです。ただし、相談は、全て無料です。
- 手数料算出の基準
まず、遺言の目的である財産の価額に対応する形で、次のとおり、その手数料が定められています。(公証人手数料令第9条別表)
目的の価額 手数料 50万円以下 3000円 50万円を超え100万円以下 5000円 100万円を超え200万円以下 7000円 200万円を超え500万円以下 13000円 500万円を超え1000万円以下 20000円 1000万円を超え3000万円以下 26000円 3000万円を超え5000万円以下 33000円 5000万円を超え1億円以下 49000円 1億円を超え3億円以下 4万9000円に超過額5000万円までごとに1万5000円を加算した額 3億円を超え10億円以下 10万9000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 10億円を超える場合 29万1000円に超過額5000万円までごとに9000円を加算した額 - 具体的な手数料算出の留意点
上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、次の点に留意が必要です。- 財産の相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言公正証書全体の手数料を算出します。
- 全体の財産が1億円以下のときは、上記(1)によって算出された手数料額に、1万3000 円が加算されます。これを「遺言加算」といいます。
- また、公正証書原本を紙に出力した場合の枚数が3枚を超える場合には、超える1枚当たり300円の手数料が加算されます。
- さらに、遺言公正証書の原本は公証人が保管するため、遺言者には、公正証書の内容を記録・記載して、その内容が公正証書の記録内容と同一であることの証明を付した電子データ又は書面(従来の正本に相当するもの)および公正証書の内容を記録・記載した電子データ又は書面(従来の謄本に相当するもの)を作成して交付することになりますので、その手数料が必要になります。
この従来の正本に相当するもの及び謄本に相当するものを電子データで発行する場合の手数料は、各1通当たり2500円となります。
また、これを書面で発行する場合の手数料は、発行された書面の枚数に1枚当たり300円を乗じた額となります。 - 遺言公正証書の作成が嘱託人の病床で行われたときは、上記(1) によって算出された手数料額に、50 %加算されることがあるほか、遺言者が、病気または高齢等のために体力が弱り、公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム、介護施設等に赴いて、遺言公正証書を作成する場合には、公証人の日当(1日2万円。ただし4時間以内の場合1万円)と、現地までの交通費が掛かります。
- 遺言公正証書の作成費用の概要は、以上でほぼご説明できたと思いますが、具体的に手数料の算定をする際には、それ以外の点が問題となる場合もあります。それらの問題については、それぞれの公証役場にお尋ねください。
Q8.口がきけない方や耳が聞こえない方でも、遺言公正証書を作成することができますか?
遺言公正証書を作成することは、可能です。
従前は、公正証書遺言は、遺言者が「口頭で」、公証人にその意思を伝えなければならず、さらに、遺言公正証書の作成後、これを「読み聞かせ」なければならないとされていました。しかし、民法の改正により、平成12 年1 月から、次のように、口がきけない方や、耳の聞こえない方でも、公正証書遺言をすることができるようになりました。
- 口頭に代わる措置
口のきけない方でも、自書のできる方であれば、公証人の面前でその趣旨を自書(筆談)することにより、また、病気等で手が不自由で自書のできない方は、通訳人の通訳を通じて申述することにより、公証人にその意思を伝えれば、公正証書遺言ができることになりました。
この結果、もともと口のきけない方も、あるいは脳梗塞で倒れて口がきけなくなったり、病気のために気管に穴を開けたりして、口のきけない状態になっている方でも、公正証書遺言ができるようになりました。
そして、実際にも、公証人が病院等に出張して、口のきけない方の公正証書遺言を作成するということも珍しくありません。 - 読み聞かせに代わる措置
また、遺言公正証書は、作成後、公証人が、遺言者および証人の前で読み聞かせることにより、その正確性を確認することになっていますが、耳の聞こえない方には、読み聞かせに代えて、通訳人の通訳または閲覧により、筆記した内容の正確性を確認していただくことができるようになりました。
4 遺言の内容
Q1.障害を抱えた子の将来の面倒を見ることを条件に、第三者に財産を与えるという遺言はできますか?
- 負担付遺贈
年老いた親にとって、障害を抱えた子の将来ほど、心配なことはないでしょう。もし、誰かその子の面倒を見てくれるという信頼できる人や団体が見つかれば、その子の面倒を見てもらう代わりに、その人や団体に、それにふさわしい財産を遺贈したいと思われるのも、ごく自然なことと思います。民法は、このように、財産の遺贈を受ける人(「受遺者」といいます。)に対し、一定の法律上の義務を負担させる「負担付遺贈」の規定を置いています(民法1002 条)。 - 遺言信託
また、負担付遺贈とは別に、遺言によって、信頼できる人や団体に、財産を譲渡(信託)するなどして、障害を持つ子のために、その財産を管理または処分し、必要なことを行ってもらう「遺言信託」という制度もあります(信託法3 条2 号)。 - 公証人にご相談を
いずれにせよ、このような遺言をする場合には、事前に、受遺者となるべき人または団体と十分に話し合っておくことが必要と思われます。
どのような方法が適しているかは、ケースによって異なるので、公証人にご相談ください。
Q2.予備的な遺言について、説明してください。
- 予備的な遺言の事例
例えば、遺言者が長男と二男(いずれも結婚して子供がいる。)に財産を相続させる遺言をした場合に、万が一、長男が遺言者よりも先に死亡したときは、遺言者としては、長男に相続させようとした財産を、孫である長男の子供に相続させたいと考えることが少なくないように思います。
しかし、そのことを遺言に記載しておかないと、当然には長男の子供に相続させることにはなりません。長男が遺言者よりも先に死亡したときは、遺言のうち、長男に相続させることにした部分が無効となるからにほかなりません。その部分は遺言をしたことになりませんので、相続人間で改めて遺産分割協議をしなければ、その帰属が決まらないことになります。
そこで、そのようなことがないように、遺言において、①「遺言者は、その有する△△ の財産を、長男に相続させる」という条項(主位的な遺言)とともに、②「遺言者は、長男が遺言者に先立って、または遺言者と同時に死亡したときは、長男に相続させるとした財産を、長男の子供に均等の割合で相続させる」という条項(予備的な遺言)を記載しておけば、万が一、長男が遺言者よりも先に死亡したときでも、長男に相続させようとした財産を、長男の子供に相続させることができることになります。
なお、長男が遺言者と同時に死亡したときも、法的には、長男が遺言者よりも先に死亡したときと同じ、長男に相続させることにした部分が無効になるので、上記② のような記載をします。
このように、遺言者が、万が一に備えて、財産を相続させ、または遺贈する者をあらかじめ予備的に定めておく遺言を「予備的な遺言」といいます。例えば、遺言者が妻に財産を相続させる遺言をする場合に、万が一、妻が遺言者よりも先に死亡した場合に、妻に相続させようとした財産を誰に相続させるのかを決めておくことも、予備的な遺言になります。 - 手数料算定における予備的な遺言の評価
公正証書遺言において、主位的な遺言と予備的な遺言とを1通の遺言公正証書に併せて記載する場合には、主位的な遺言により手数料を算定し、予備的な遺言については手数料の算定をいたしません。したがって、予備的な遺言を記載したとしても、遺言の目的である財産の価額に対応する手数料の額が増えることはありません。
これに対し、まず、主位的な遺言のみの遺言公正証書を作成し、後日になって、予備的な遺言を追加するために、予備的な遺言の遺言公正証書を作成する場合には、予備的な遺言について手数料の算定をすることになりますので、ご留意ください。
Q3.遺言によって、妻に対し、建物に居住する配偶者居住権を取得させることができますか?
- 配偶者居住権
民法の改正により、令和2 年4 月から、配偶者居住権が認められるようになり、要件を満たせば遺言によって取得させることができます。その要件とは、①相続開始時に、遺言者が対象建物を所有すること、②相続開始時に配偶者以外の者と対象建物を共有していないこと、③相続開始時に配偶者が対象建物に居住していることです(民法1028 条)。
したがって、遺言者は、例えば、子供に対し、その所有する建物および敷地を相続させる(遺贈する。)とともに、配偶者に対し、その建物に関する配偶者居住権を遺贈する旨の遺言をすることによって、配偶者が、長期間にわたって、住み慣れた居住環境での生活を継続できるようにすることが可能になったわけです。 - 手数料算定における配偶者居住権の評価
公正証書遺言の手数料の算定に当たっては、配偶者居住権は、居住建物およびその敷地(または敷地利用権。以下同じ。)の合計評価額の3割に相当する額を配偶者居住権の価額として、手数料の計算を行います。他方、居住建物およびその敷地を取得する者については、居住建物およびその敷地の合計評価額の7割に相当する額をその取得価額として、手数料の計算を行うことになります。
詳しくは、公証人にお尋ねください。
5 自筆証書遺言と公正証書遺言の相違
Q1.自筆証書遺言は、どのように作成するのですか?
- 自筆証書遺言の作成
自筆証書遺言は、遺言者が、紙に、自ら遺言の内容の全文を手書きし、かつ、日付および氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成します。
なお、平成31 年1 月からは、民法の改正により、遺言書にパソコン等で作成した財産目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産登記事項証明書等を財産目録として添付したりすることが認められるようになりました(民法968 条)。この場合、これらの財産目録には、遺言者が毎葉(手書きでない部分が両面にあるときは、その両面)に署名し、押印しなければなりません。
このように、添付する財産目録については、手書きでなくてもよくなったのですが、財産目録以外の遺言書の全文(例えば、財産目録記載のどの財産を誰に相続させ、または遺贈するという記載を含みます。)は、遺言者が手書きしなければなりません。これをパソコン等により記載したり、第三者に記載してもらったりした場合には、遺言が無効になります。 - 自筆証書遺言の保管
自筆証書遺言は、遺言者が自ら保管するほか、法務省令で定める様式に従って作成した無封の自筆証書遺言であれば、自筆証書遺言保管制度を利用して法務局で保管してもらうこともできます(Q3参照)。
Q2.公正証書遺言と自筆証書遺言には、どのような違いがありますか?
公正証書遺言と自筆証書遺言には、次のような違いがあります。
- 無効となる危険性の有無
自筆証書遺言は、内容が簡単な場合はともかく、そうでない場合には、法律的に見て不備な内容になってしまう危険性があり、後に紛争の種を残したり、無効になってしまったりする場合もあります。しかも、自筆証書遺言は、誤りを訂正した場合には、遺言者が、その訂正した箇所を指示し、これを訂正した旨を付記して、そこにも署名し、かつ、その訂正した箇所に押印をしなければならないなど、方式が厳格なので、方式不備で無効になってしまう危険も付きまといます(民法968 条)。
これに対し、公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が関与するので、複雑な内容であっても、法律的に見てきちんと整理した内容の遺言にしますし、もとより、方式の不備で遺言が無効になるおそれもありません。また、公正証書遺言は、遺言をその場で訂正する場合でも、公証人が責任をもって訂正手続を行うので、安心です。 - 字が書けない場合
自筆証書遺言は、財産目録以外は全文を手書きしなければならないので、当然のことながら、病気等で手が不自由になり、字が書けなくなった方は、利用することができません。
これに対し、公正証書遺言では、体力が弱り、あるいは病気等のために、手書きすることが困難となった場合でも、公証人に依頼することによって、遺言をすることができます。遺言者が署名することさえできなくなった場合でも、公証人が、遺言公正証書に、その旨を記載するとともに、「病気のため」などとその理由を付記し、職印を押捺することによって、遺言者の署名に代えることができることが法律で認められています。公証実務では、これに加えて、公証人が遺言者の氏名を代署し、その代署した氏名の次に、遺言者に押印してもらうことが行われており、遺言者が押印することもできないときは、遺言者の意思に従って、公証人等が遺言者の面前で遺言者に代わって押印することができます。 - 検認手続の要否
自筆証書遺言は、その遺言書を発見した者が、家庭裁判所にこれを持参し、その遺言書を検認するための手続を経なければなりません(ただし、Q3の法務局における遺言書保管制度を利用した場合には、検認の手続が不要です。)。
これに対し、公正証書遺言では、家庭裁判所における検認の手続が不要ですので、相続人等の負担が少なくて済みます。 - 証人の要否
自筆証書遺言は、証人が不要です。
これに対し、公正証書遺言では、証人2名の立会いが必要です。証人が立ち会うことによって、遺言者の真意を確認し、手続が適式に行われたことが担保されます。 - 保管上の危険性の有無
自筆証書遺言は、自宅で保管していた場合には、これを紛失し、あるいは、発見した者が自分に不利なことが書いてあると思ったときなどに、破棄したり、隠匿や改ざんをしたりしてしまう危険性がないとはいえません。
これに対し、公正証書遺言では、遺言書の原本が必ず公証役場に保管されるので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。 - 費用の有無
自筆証書遺言は、自分で手書きすればよいので、費用も掛からず、いつでも作成することができます(ただし、Q3の法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用する場合には、若干の手数料が必要です。)。
これに対し、公正証書遺言では、政令で定められた手数料が必要です。ただし、相談は無料です。
Q3. 自筆証書遺言について法務局における遺言書保管制度を利用した場合に比べ、公正証書遺言には、どのような特徴やメリットがありますか?
自筆証書遺言については、法務局において保管する遺言書保管制度が創設され、令和2年7月から運用が開始されました。その詳細は、法務省のホームページの説明を御覧ください。この保管制度を利用した場合には、公正証書遺言の場合と同様に、遺言書の紛失やこれを発見した者による破棄、隠匿、改ざん等の危険を防止することができ、また、家庭裁判所における検認の手続も不要となります。
一方、公正証書遺言については、遺言書保管制度が始まった現在でも、次のとおり、自筆証書遺言に比べ、メリットが多く、安全確実な遺言の方法であるということができます。
- 自書(手書き)の必要性の有無
遺言書保管制度を利用した場合でも、自筆証書遺言である以上、遺言者が財産目録以外の全文を手書きしなければならないことについては、変わりがありません。しかも、遺言書保管制度を利用するためには、通常の自筆証書遺言ではなく、法務省令で定める様式に従って作成した自筆証書遺言でなければならず、また、遺言書は、封筒に入れて封印した状態ではなく、無封のものでなければなりません。
これに対し、公正証書遺言では、公証人が遺言者から告げられた内容を遺言書に記載しますので、遺言者が手書きするのは、署名部分だけとなります。しかも、遺言者が病気等のために署名をすることができないときは、公証人が遺言者の署名に代わる措置をとることが法律上認められているので(Q2の2参照)、このときは、遺言者は、自ら署名する必要もありません。 - 高度な証明力の有無
遺言書保管制度を利用する場合でも、法務局では、自筆証書遺言の内容に関する質問や相談には応じることができません。つまり、自筆証書遺言の内容については、遺言者の自己責任ということになります。
これに対し、公正証書遺言では、法律の専門家である公証人が、遺言の内容に関する質問や相談に無料で応じるとともに、具体的に遺言書を作成する場合にも、遺言の内容をきちんと整理し、遺言者の遺言能力(有効な遺言をすることができる判断能力)の有無など遺言が法律的に有効であるために必要な事項を慎重にチェックします。このため、公正証書遺言には、遺言者が意思表示した遺産分け等について、高度な証明力(実質的な証明力)が認められます。 - 出張の有無
遺言書保管制度は、自筆証書遺言の保管の申請時に、遺言者本人が法務局に出向かなければなりません。法務局の職員が遺言書保管のために出張することはないので、遺言者が病気等のために法務局に出向くことができないときは、この制度を利用することができません。
これに対し、公正証書遺言では、遺言者が高齢や病気等のために公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が遺言者のご自宅や老人ホーム、介護施設、病院等に出張して、遺言書を作成することができます。 - 遺言書の写しの入手方法
遺言書保管制度では、法務局で保管された自筆証書遺言について、その写しは手元に残りません。遺言者が死亡した後に、相続人等が、遺言者の出生から死亡までの戸籍等の謄本一式等を添付して、遺言書情報証明書(遺言書の画像情報を表示したもの)の交付を申請し、その証明書の交付を受け、これを用いて遺言執行を行います。
これに対し、公正証書遺言では、遺言書の作成時に、遺言書の正本1通と謄本1通の交付を受けるのが通常であり、これを利用して遺言執行を行うので、遺言者の死後に、改めて遺言書の謄本(写し)を請求する必要はありません。
6 秘密証書遺言と公正証書遺言の相違
Q1. 秘密証書遺言は、どのように作成するのですか?
- 秘密証書遺言の作成手順
秘密証書遺言は、遺言者が、遺言の内容を記載した書面に署名押印をし、これを封筒に入れて、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印をした上、公証人および証人2名の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申し述べ、公証人が、その封紙上に日付および遺言者の申述を記載した後、遺言者および証人2名とともにその封紙に署名押印をすることにより、作成します。
なお、民法では、「証人二人以上」と定められていますが、公証実務では、証人が3名以上になることはなく、証人2名で秘密証書遺言が作成されています。
以上の手続を経由することにより、その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にでき、かつ、遺言の内容を誰にも明らかにせず、秘密にすることができます。 - 自書(手書き)以外も可能
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、自書である必要はないので、遺言書は、パソコン等を用いて文章を作成しても、第三者が筆記したものでも、差し支えありません。
Q2. 秘密証書遺言には、どのような問題点がありますか?
秘密証書遺言には、公正証書遺言と異なり、次のようなリスク等があります。
- 無効となる危険性の存在
秘密証書遺言では、公証人は、その遺言書の内容を確認することができないので、遺言書の内容に法律的な不備があったり、無効となったりする危険性がないとはいえません。 - 保管上の危険性の存在
秘密証書遺言は、遺言者自身が保管する必要があります。そのため、これを紛失し、あるいは発見した人が自分に不利なことが書いてあると思ったときなどに、破棄したり、隠匿や改ざんをしたりしてしまう危険性がないとはいえません。 - 検認手続の必要性
秘密証書遺言は、法務局において遺言書を保管する遺言書保管制度を利用することができません。したがって、秘密証書遺言は、遺言書保管制度を利用しなかった自筆証書遺言と同じように、この遺言書を発見した人が、家庭裁判所に届け出て、検認手続を受けなければなりません。
7 遺言の検索、謄本の請求及び保存期間
Q1. 亡くなった方について、公正証書遺言が作成されているかどうかを調べることができますか?
- 公正証書遺言の検索システム
平成元年以降に作成された公正証書遺言については、日本公証人連合会において、全国の公証役場で作成した遺言公正証書の情報(作成公証役場名、公証人名、遺言者の氏名及びよみがな、生年月日、性別、国籍、作成年月日等)を管理しております。全国の公証役場において、この情報に基づき、遺言公正証書の有無及び保管公証役場を検索することができますので、お近くの公証役場にお申し出ください。遺言検索の申出は、無料です。 - 検索の方法及び必要書類等
遺言検索の申出は、秘密保持のため、相続人等の利害関係人のみが公証役場(公証人)に対してすることができます。申出の際の必要書類は、①遺言者が死亡した事実を証明する書類(除籍謄本等)、②遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本、③申出人の本人確認の書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書又は実印及び印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの))です。
なお、遺言者が亡くなる前は、遺言検索の申出は遺言者本人に限られています。
Q2. 母の遺言公正証書が見つかりません。どうしたらよいのでしょうか?
上記Q1のとおり、遺言者の相続人は、遺言検索の申出をすることができます。遺言検索は全国どこの公証役場でもできますので、お近くの公証役場に出向いて遺言検索の申出をしてください。遺言検索の結果、遺言書を保管している公証役場が明らかになれば、保管公証役場に対して遺言公正証書の謄本を請求することができます。
Q3. 遺言公正証書の謄本の請求は、遺言書を保管している公証役場に出向く必要がありますか?
遺言公正証書の謄本の請求は、郵送によっても可能です。
謄本請求の際の必要書類は、①謄本請求書(本人確認の資料として、印鑑登録証明書を用いる場合は実印を押印してください。それ以外の運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書の場合は、押印は不要です。)、②遺言者が死亡した事実を証明する書類(除籍謄本等)、③遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本、④謄本請求者の本人確認の書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書または実印の場合は印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの))です。
なお、謄本請求者の本人確認の資料として、マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書を利用した場合には、補充的に、テレビ電話を利用して本人確認を行うことになります。
遺言書を保管している公証役場が分かれば、事前に保管公証役場に連絡を入れて、その旨をご相談ください。
Q4. 公正証書遺言は、どのくらいの期間、保存されるのですか?
- 公正証書の保存期間に関する定め
公正証書の保存期間は、公証人法施行規則70条で、20年と定められています。さらに、同規則では、特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間は保存しなければならないと定めています。 - 公証実務における遺言公正証書の保存期間
遺言公正証書は、上記規則の「特別の事由」に該当すると解釈されており、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存する取扱いとしています。