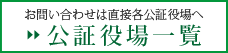Q3. 確定日付の対象となる文書は、どのようなものですか?
私文書(公文書でない文書)に限られます。官公署または官公吏がその権限に基づき作成する文書(公文書)は、その日付が確定日付となりますので、公証人は確定日付を付することはできません。
例えば、不動産の登記事項証明書は、公務員である登記官がその権限に基づいて作成するものですから、その証明書に記載された作成日付が確定日付となり、公証人はこれに確定日付を付与することはできません。
私文書は、文字その他の記号により、意見、観念または思想的意味を表示しているものであることが必要です。
図面または写真自体は、意見、観念等を表示しているとは言えませんので、それ自体に確定日付を付することはできません。しかし、例えば、写真を台紙に貼って割印し、台紙に撮影の日時場所等のデータを記入した証明文を記載して記名押印する方法で私署証書とした場合には、これに確定日付を付与することができます。
文書のコピー自体には、確定日付を付与することはできません。この場合は、そのコピー上に写しを作成した旨を付記するか、または、同様の説明文言を表示する証書を添付するなどして割り印し、それらの説明文書に確定日付を付与することになります。
内容の違法な文書、無効な法律行為を記載した文書であることが明らかなものは、確定日付を付与することはできません。
作成年月日欄があるのに具体的な年月日の記載を欠いたものは、公証人が確定日付を付与した後にその作成年月日を補充して記載することにより混乱が生ずるのを防止するため、作成年月日欄に棒線を引いてもらうか、空欄である旨付記した上で確定日付を付与する取扱いになっております。
後日の記入を前提とするような、形式上未完成な文書は、そのままでは確定日付を付与することはできません。
作成者の署名または記名押印のあるものでなければなりません。
記名はあるが押印を欠くもの、押印はあるが作成者の名称を欠くものは補充を求めた上、確定日付を付与する取扱いとなっております。
署名または記名は、氏名をフルネームで記載する必要はなく、氏または名のみでもよく、通称、商号、雅号、仮名でも差し支えありません。